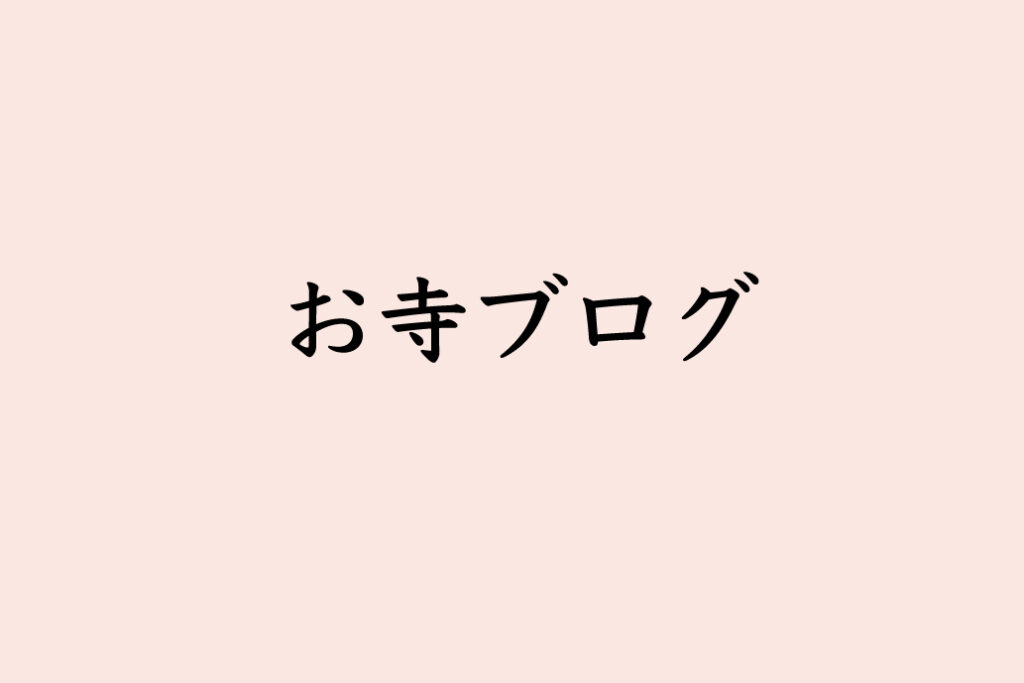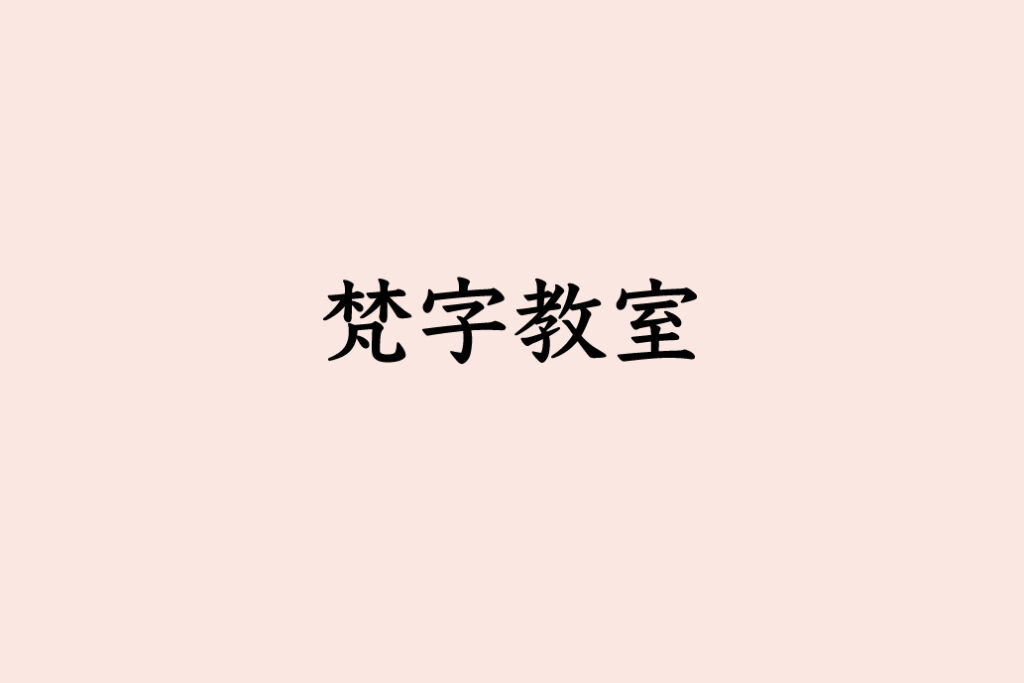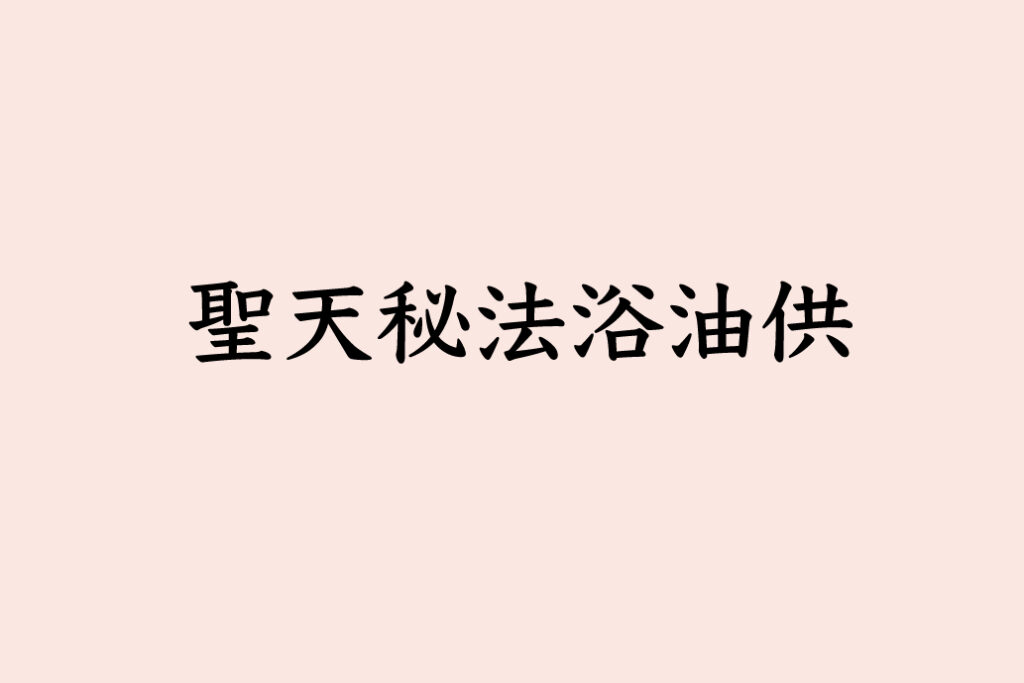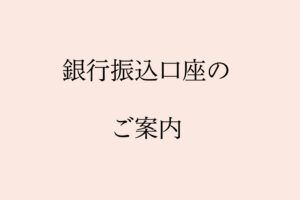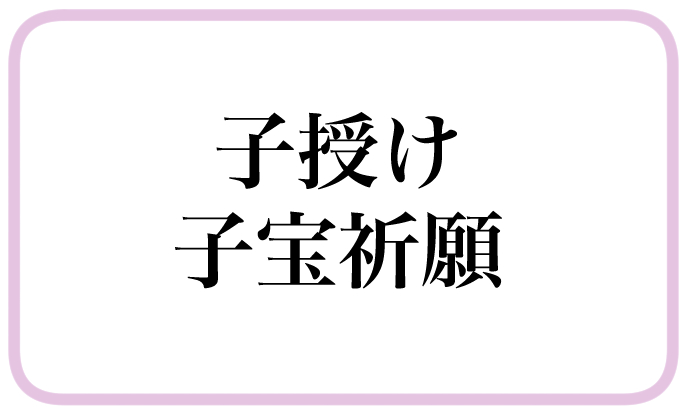
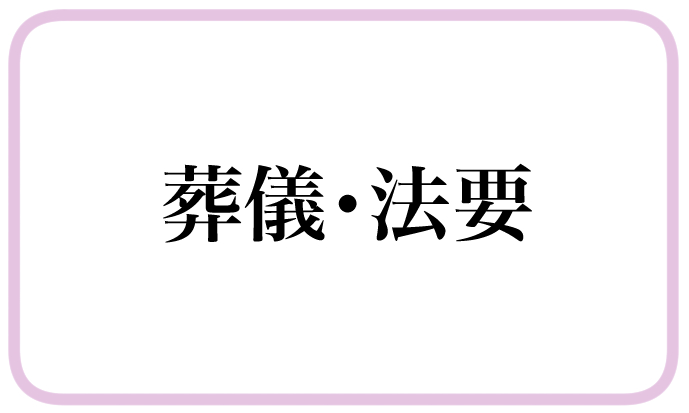
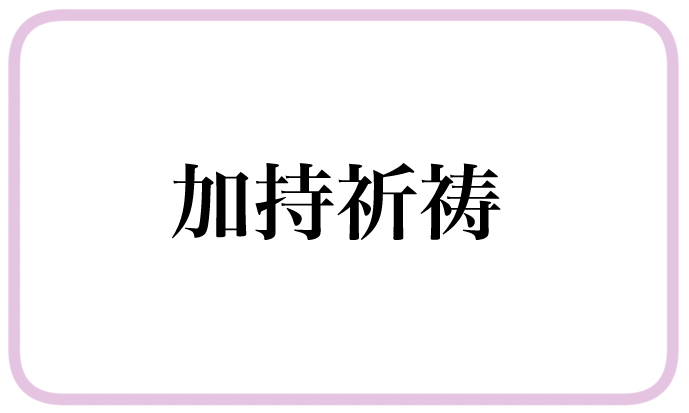
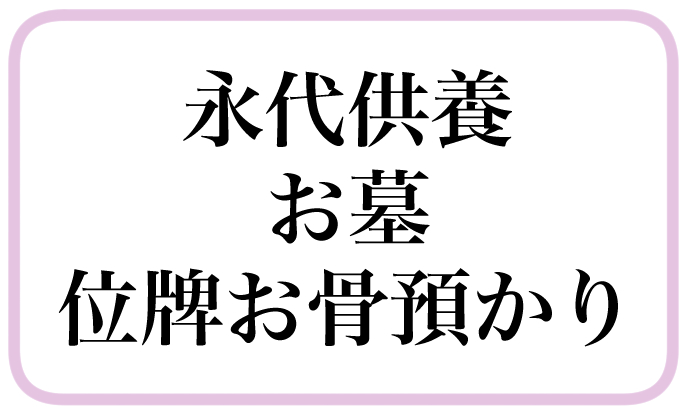
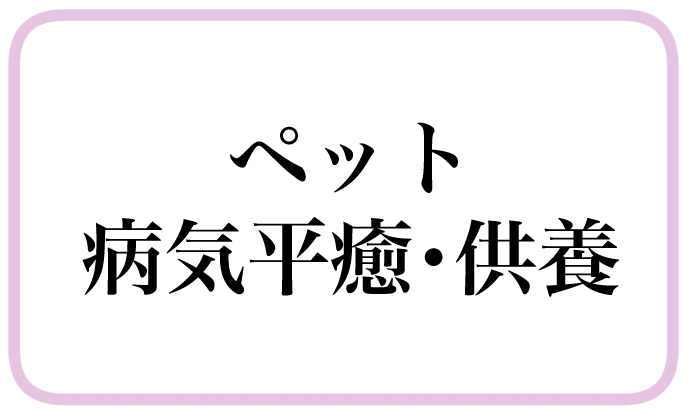
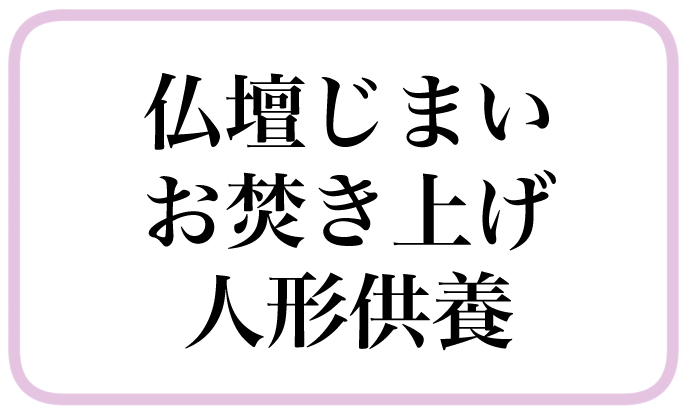



護国院は真言宗のお寺で、愛媛県東温市上村に位置します。
愛媛の本院とは別に、奈良県橿原市一町にも礼拝所があります。
護国院は、220年前になりますが文化2年(1805年)に本尊金毘羅権現様を開眼し開基されました。
その当時は香川の金毘羅さん信仰が盛んでありました。護国院の北の国道は讃岐街道と呼ばれ、金毘羅権現を本尊とする寺院が散見されるほどの香川の金毘羅宮に続く街道です。
また当時、当山派の修験道が地域一帯で盛んで、毎年奈良の大峰山の入峰修行にたくさんの信者さんが行かれている記録が当院にも残っています。
私は現在八代目住職ですが、五、六代目の祖父や曽祖父の時は、祈祷寺院こんぴら寺として地域を越えて親しまれ、愛媛県の島嶼部(現在の大三島など)までお札を持って加持をしに出かけて行っていたという話も聞いております。
このように広く地域をカバーする祈祷寺院としての役割をになっておりました。
地所も当院の下にある貯水池、彦八池が造成されたために、現在の場所に移転いたしました。
その後、お寺が荒れた時期には庫裡が人手に渡ってしまい、ご来山者の方にはご不便もお掛けしております。
しかし上村地区の篤信の方々に駐車場の便宜や境内地の草刈りなど、様々なご助力を頂いてお寺としてのお役目を続けさせていただいており、遠方からのご来寺の方も増え、現在に至ります。
本尊護摩供の祈願祈祷、追善供養の回向を通じ、宗祖弘法大師、並びに聖寳理源大師(京都伏見の醍醐寺開祖、弘法大師実弟真雅師の御弟子です。かの菅原道真公のご学友です。因みに当院は真言宗醍醐派です。)の教理をもとに、みなさんの心の安寧と生きる原動力をますます増して参ります。
『 困った時には護国院、良いこと願えば金毘羅さん 』と親しまれる様な地元のお寺を目指して、地道に精進邁進して参ります。
これからもどうかご指導ご鞭撻を頂ければ幸いです。護国院をどうぞよろしくお願いします。
住職:武智宏教
修験道とは
修行の道場である霊山での厳しい修行(斗藪:とそう)を積み重ね、人々の求めに応じて現世での利益を祈りだす呪術力の獲得を追求する、仏教の一分野です。
その名の由来は、現世利益を求める祈りでもたらされる「験」を「修める」行為からきています。ですので、古来より獲得・発揮される験力を評価します。山岳での斗藪は、数多ある手段の一つで、それによって験力を高めていきます。
験力とはつまり、祈る力(呪術力)です。それを高める(斗藪)方法は、それぞれの師(先達)にお尋ね下さい。
後世に至って教義なども整えられるようになり、徐々に「道」としてのかたちもできてきました。
参考:「大日本史料」承和二年(1208年)編纂の中に、僧徒には四種類ある。一つには顕宗、二つには密宗、三つには験者、四つには説経師である。顕宗の僧は成業をなし終わったもの、密教の僧は灌頂をなし終わったものである。験者は密宗に属し、説法師は顕宗に属する。
山伏とは、山岳での厳しい修行をする者をさします。現在当山派では、一定のルールで入峰装束を決めております。峰入での作法や修行内容もさまざまありますので、それぞれの師(先達)に伝授を受けてください。11世紀に著された「新猿楽記」によると、理想的な密教僧が行う修行に「山臥修行」があると記されています。それは、山でよこたわる(寝食をする)からはじめて、山にいだかれ、山と一体になる(この世界全てと同一になる)修行です。自然と一体になるということは、自分の周囲と一体となること、つまり家庭や自身の交友関係、会社、地域と一体となることです。日常で疲弊した自分を山野でリフレッシュすることでもあります。(キャンプみたいなものですが、それで良いと思います。)
周囲と一体となることの良いところは、周囲の人々の心持ちがわかるので、周囲の人々の心持ちにかなったことができる、つまり愛される人になれるということです。
もし山伏にご興味があれば、行事内容と適性判断致しますので、お気軽にご連絡下さい。
(女人禁制ではないところでも修行できます。)
斗藪の道場について
古来より大峰山を中心とする吉野、熊野や葛城山系が修験者で賑わいました。護国院は、文化元年(1804年)の入峰より当山方の修験道(仏道修行)を取り入れております。修行道場は、葛城山系と大峰山系などです。
「新猿楽記」に登場する「山臥修行」の地は、度々通大峯・葛木、踏辺道、年々熊野、金峯、越中立山、伊豆走湯、根本中堂、伯耆大山、富士御山、越前白山、高野、粉河、箕面、葛川等之間、無不競行挑験、とあります。現在も霊山として、修験者が入峰しているところです。
修験道の教派について
現在では様々に分かれておりますが、近世では、当山派(真言宗系、棟梁:醍醐寺三宝院門跡)と本山派(天台宗系、棟梁:聖護院門跡)の二派の傘下に収められていました。(例外はあります。)ただし江戸時代初期以前にはそういう区分ではなかったと推察されます。
護国院は、当山派で醍醐寺の末寺になります。
奈良別院では、不動明王様、聖天様、十一面観音菩薩様、延命地蔵菩薩様、水子地蔵菩薩様、龍神様、諸佛をお祀りしております。
聖天様(歓喜天)はそのお力で、みなさんの現世利益を叶えることで財産的な余裕を得させ、みなさんに早く菩薩行を全うしてもらおうと思召されておられます。
なので少し無理というお願いも、聖天様におすがりすれば叶うといういわれがあるのです。
お不動様は、間違った方向に行ってしまう人々を正しい方向に導く仏様です。
悪い行いからくる災難を除いて、幸せな道へと歩ませてくれます。
お地蔵様は大地を司る菩薩様です。
大地は様々な生命を育みますが、上手にコントロールされるのがお地蔵様の力ですので延命地蔵さまと呼ばれます。
子どもの供養は水子地蔵菩薩さま。子授けの功験もございます。
護国院では、昔ながらの檀家制度は取っておらず、入檀料や護持会費はありません。
必要とされた時に一度だけでもお気軽に利用できるようにしております。
境内の修繕は追いついておりませんがご容赦くださいませ。
ご祈祷やご供養、あらゆるご相談事など遠慮なくご連絡ください。
宗教法人 護国院
住職 武智 宏教(たけち こうきょう)

聖天秘法浴油供のご案内

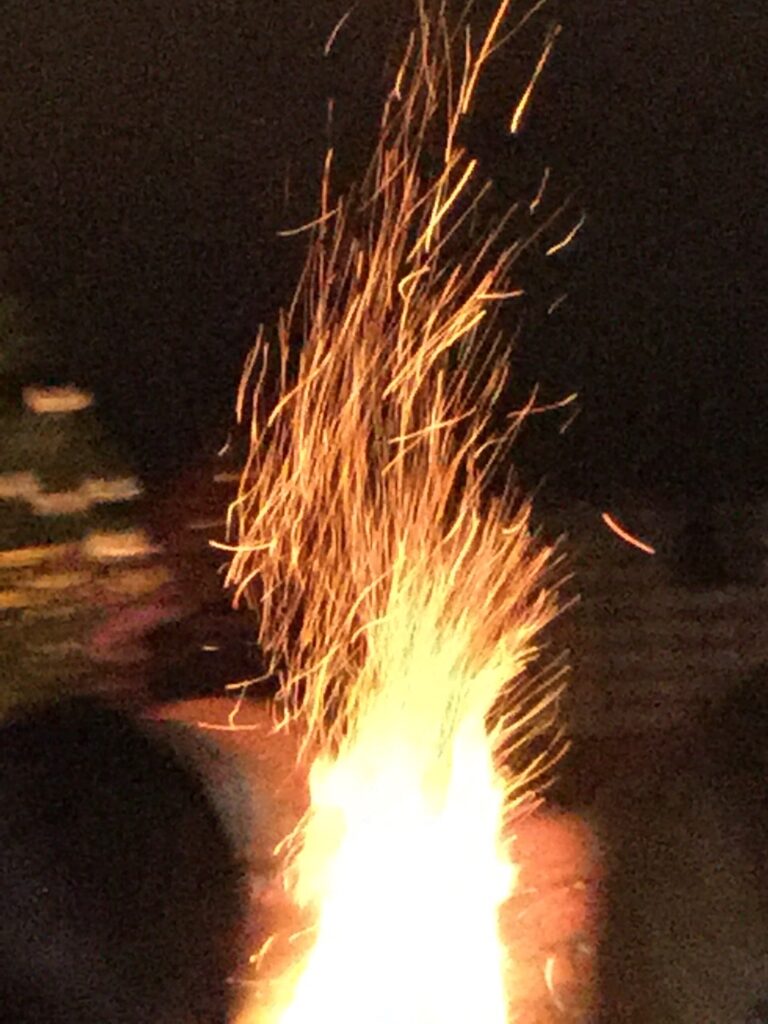

宗教法人 護國院
■愛媛本院
〒791-0221 愛媛県東温市上村乙21番地
電話089−964−8838
■奈良別院
〒634-0824 奈良県橿原市一町877番地
電話0744−33−7056
FAX0744−33−7172
■東京別院 不動心院 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号VORT秋葉原Ⅳ2F 電話とFAX 050-3183-9174
【ご案内】本院や別院へのご連絡は、副住職の武智 叡倫(えいりん)まで 電話 090-6606-7233
メール gokokuin2@gmail.com
24時間遠慮なくお気軽にお問い合わせください。